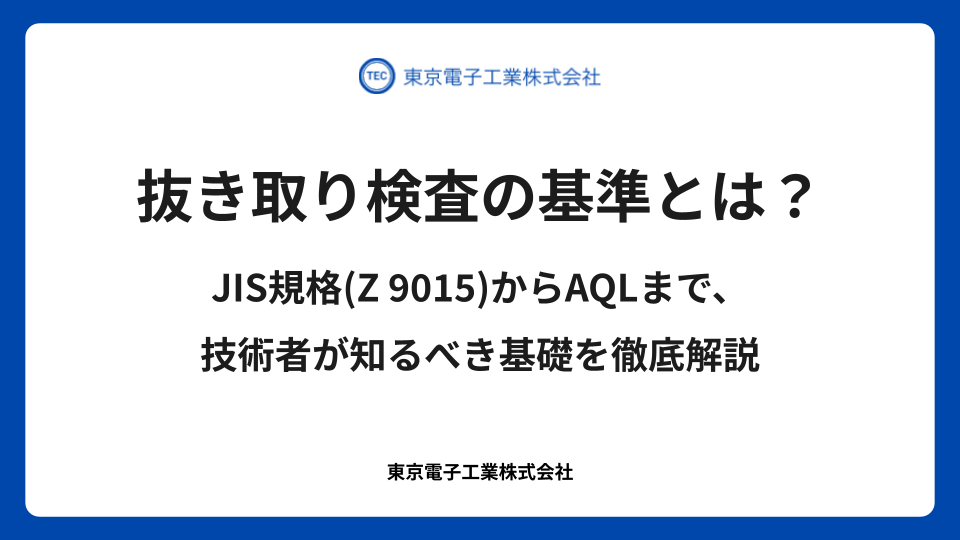
「この抜き取り検査の基準は、本当に妥当なのだろうか?」
「社内でこの基準の根拠をどう説明すれば納得してもらえるだろうか?」
製造業の品質保証の現場で、このような疑問や課題を感じたことはありませんか。抜き取り検査は、品質とコストのバランスを取る上で不可欠な手法ですが、その「基準」の設定は非常に繊細で、企業の信頼性を左右する重要な要素です。
感覚や慣例で基準を決めてしまうと、不良品の流出リスクを高めたり、逆に過剰な検査でコストを圧迫したりする可能性があります。
本記事では、製造業の技術部門ご担当者様に向けて、抜き取り検査の「基準」に関するあらゆる疑問を解消します。
関連記事:抜き取り検査とは?目的、種類、全数検査との違いを徹底解説
なぜ、製造業において抜き取り検査の「基準」が重要なのか?
製造プロセスにおいて、品質とコストは常にトレードオフの関係にあります。この二律背反の課題に対して、最適なバランス点を見つけ出すための羅針盤となるのが、抜き取り検査における客観的な基準です。
もし、この基準が曖昧だった場合、企業は以下のような深刻なリスクに直面します。
- 不良品の流出: 顧客の信頼を失墜させ、ブランドイメージを大きく損ないます。リコールや賠償問題に発展するケースも少なくありません。
- 手戻り・再検査コストの増大: 不合格ロットの処置が不明確なため、工程に手戻りが生じ、生産計画を圧迫します。
- 機会損失: 過剰に厳しい基準を設定してしまうと、本来は合格とすべきロットまで不合格となり、生産効率の低下や出荷遅延による販売機会の損失につながります。
逆に、JIS規格のような客観的で合理的な基準を設けることで、担当者は自信を持ってロットの合否を判定できます。さらに、品質会議や監査、顧客への説明といった場面でも、その基準の正当性を論理的に示すことができ、社内外への強力な説明責任を果たすことが可能になるのです。
抜き取り検査の基本 | 全数検査との違いと使い分け
抜き取り検査とは?その定義と目的
抜き取り検査とは、生産された製品の集合(ロット)から、あらかじめ定められた方式でサンプル(試料)を抜き取って検査し、その試験結果をロット全体の品質基準と比較して、ロットの合格・不合格を判定する手法です。
統計学的な考えに基づいており、少ないサンプルでロット全体の品質を合理的に推定することを目的とします。
全数検査とのメリット・デメリット比較
品質検査には、抜き取り検査の他に全数検査があります。両者の違いを理解し、製品の特性や目的に応じて使い分けることが重要です。
| 比較項目 | 抜き取り検査 | 全数検査 |
|---|---|---|
| 品質保証レベル | ロットの品質を統計的に保証(不良の流出リスクはゼロではない) | 原則として不良品の流出はない(※見逃しがなければ) |
| コスト(費用・時間) | 低い | 高い |
| 検査員の負担 | 少ない | 多い |
| 破壊検査の適用 | 可能 | 不可能 |
| 主な目的 | 工程が安定していることの確認、品質とコストのバランス最適化 | 不良品の流出防止、市場での絶対的な安全・品質の確保 |
抜き取り検査が有効なケース、不向きなケース
【有効なケース】
- ねじや電子部品など、ロットの製品数が非常に多い場合
- 強度試験や耐久試験など、製品を破壊しなければ検査できない場合
- 検査項目が多く、全数検査ではコストや時間が見合わない場合
- 工程が安定しており、品質のばらつきが小さいことが分かっている場合
【不向きなケース】
- 人命に関わる医療機器や、安全性が最優先される自動車の重要保安部品
- 1つの不良がシステム全体に致命的な影響を与える製品
- 顧客との契約で全数検査が義務付けられている場合
抜き取り検査の国際的指標「AQL(合格品質基準)」とは
抜き取り検査の基準を語る上で欠かせないのが、AQL(Acceptable Quality Level:合格品質水準)という国際的な指標です。
AQLとは何か?
AQLとは、「ある程度の不良がその中に含まれていても、そのロットを合格と見なせる、許容可能な品質レベル」を指します。
重要なのは、AQLが「不良ゼロ」を目指すものではないという点です。これは、生産者と消費者の間で「このAQLの基準を満たしていれば、そのロットは合格品として受け入れましょう」という一種の『合意』を示すものです。例えば「AQL 1.0%」と設定した場合、「不良率が1.0%以下のロットであれば、高い確率で合格となる」という検査方式を意味します。
AQLの決め方のポイント(致命的欠点、重欠点、軽欠点)
AQLは、製品に求められる品質レベルや欠点(不適合)の重要度に応じて設定します。一般的に、欠点は以下の3つに分類され、それぞれに異なるAQL値を設定します。
- 致命的欠点 (Critical Defect): 使用者に危険を及ぼす、あるいは製品が全く機能しない欠点。(例:食品への金属片混入、ブレーキ部品の亀裂)。通常、AQLは適用されず、発見次第即不合格となります。
- 重欠点 (Major Defect): 製品の性能を著しく低下させ、通常の使用に耐えられない欠点。(例:電子機器の電源が入らない、縫製品の大きな破れ)。一般的に低いAQL値(例:AQL 0.65%, 1.0%)が設定されます。
- 軽欠点 (Minor Defect): 製品の外観を損なうが、性能にはほとんど影響しない欠点。(例:樹脂製品の僅かなバリ、塗装の微小なムラ)。比較的高いAQL値(例:AQL 2.5%, 4.0%)が設定されます。
AQLと生産者リスク(α)、消費者リスク(β)の関係性
抜き取り検査は統計的な手法であるため、100%完璧な判定はできません。そこには2つのリスクが伴います。
- 生産者リスク (αリスク): 本来は合格とすべき良い品質のロットを、偶然悪いサンプルが抜き取られたために不合格と判定してしまう確率。
- 消費者リスク (βリスク): 本来は不合格とすべき悪い品質のロットを、偶然良いサンプルが抜き取られたために合格と判定してしまう確率。
AQLを用いた抜き取り検査は、これらのリスクを特定の水準以下に抑えるように設計されています。この関係性を示したものがOC曲線(検査特性曲線)であり、ロットの不良率に対して合格する確率をグラフ化したものです。
JIS Z 9015(計数抜取検査手順)とは
AQLという考え方を、具体的な検査手順に落とし込んだものがJIS Z 9015です。
JIS Z 9015の概要と、なぜ多くの企業で採用されるのか
JIS Z 9015は、AQL指標に基づいた計数規準型の抜き取り検査についての手順を定めたものです。多くの企業で採用される理由は、その客観性と網羅性にあります。ロットのサイズや要求品質(AQL)に応じて、統計的に合理的なサンプルサイズと合否判定基準を誰でも導き出せるため、属人性を排除した公平な検査が実現できます。国際規格であるISO 2859-1を基にしているため、グローバルな取引においても信頼性の高い基準として通用します。
JIS Z 9015の規格票(付属書)を読み解くには、主に以下の3つの要素を順に理解する必要があります。
検査水準(特別検査水準、通常検査水準)とは
検査の厳しさを決めるもので、通常検査水準(I, II, III)と特別検査水準(S-1, S-2, S-3, S-4)があります。
- 通常検査水準: 主要な検査に用いられます。特別な理由がない限り、コストと保護レベルのバランスが良い「II」が一般的に推奨されます。より厳しい検査が必要な場合はIII、緩やかな場合はIを選択します。
- 特別検査水準: 破壊検査など、検査コストが非常に高い場合や、ごく簡単なチェックで済ませたい場合に用いられます。サンプルサイズが小さく抑えられます。
サンプル文字(アルファベット)の役割
「ロットのサイズ」と選択した「検査水準」が交差するマスから、A~Rのサンプル文字を特定します。この文字が、次のステップで用いる主抜取表の「行」を決定する重要なキーとなります。
合格判定個数(Ac)と不合格判定個数(Re)の決定方法
JIS Z 9015を使い、先ほど特定した「サンプル文字」の行と、設定した「AQL」の列が交差する箇所を見ます。そこに記載されているのが、「サンプルサイズ(n)」と「Ac (Acceptable number): 合格判定個数」、「Re (Rejectionable number): 不合格判定個数」です。
- Ac: 抜き取ったサンプル中の不適合品数が、この数以下であればロットは合格。
- Re: 抜き取ったサンプル中の不適合品数が、この数以上であればロットは不合格。
【実践編】自社に最適な抜き取り検査基準を設定する4ステップ
それでは、これまでの知識を使って、実際に抜き取り検査の基準を設定するプロセスを見ていきましょう。
前提条件:
- 製品: 小型モーターに使用する特殊ネジ
- 納入単位: 1ケース 10,000個
- 品質要求: ネジの長さに軽微な不適合がある(軽欠点)が、機能に大きな影響はない。AQLは1.5%と設定。
Step1:ロットのサイズを定義する
今回は1ケースが1つのロットとなるため、ロットのサイズは10,000個です。
Step2:検査水準を選択する(通常検査IIが基本、その理由とは)
特に指定がないため、最もバランスの取れた「通常検査水準 II」を選択します。
Step3:AQL(合格品質基準)を設定する
前提条件より、AQLは1.5%とします。
Step4:抜取表から「サンプルサイズ」と「合格判定個数」を導き出す
サンプル文字の特定(表1):
- 「ロットのサイズ」の行で「3201~10000」を探します。
- 「通常検査水準」の列で「II」を探します。
- 両者が交差するマスにあるサンプル文字は「L」です。
サンプルサイズとAc/Reの決定(表2-A):
- 「サンプル文字」の列で「L」を探します。この行から、サンプルサイズ(n)が200個であることがわかります。
- 「L」の行を右に見ていき、「AQL」の列で「1.5」を探します。
- 両者が交差するマスを見ると、Ac = 7, Re = 8 となっています。
【結論】
このケースにおける抜き取り検査の基準は、「10,000個のロットからランダムに200個を抜き取り、その中に不適合品が7個以下であれば合格、8個以上であれば不合格とする」となります。
抜き取り検査の精度を左右する運用上の注意点
正しい基準を設定しても、その運用方法が不適切では意味がありません。ここでは3つの重要なポイントを解説します。
最も重要な「サンプリングのランダム性」をどう確保するか
抜き取ったサンプルは、ロット全体の品質を代表していなければなりません。箱の上部だけから抜き取るようなことをすると、偏った結果しか得られません。ロット全体から満遍なく抜き取るランダムサンプリングが不可欠です。乱数表を使ったり、生産時間や場所を区切って系統的に抽出したりする工夫が求められます。
不合格ロットの適切な処置
不合格となったロットをどう扱うか、あらかじめルールを決めておく必要があります。
- 全数選別: ロットの全数を検査し、不適合品を取り除いて適合品のみを出荷する。
- 廃棄: ロット全体を廃棄する。
- 手直し: 不適合品を修理・修正して良品にする。
- 格下げ: 正規の製品としては使わず、別の用途に転用する。
製品の価値や手直しのコストなどを考慮し、最適な処置を判断します。
定期的な検査基準の見直しの必要性
一度設定した基準が永遠に最適とは限りません。製造プロセスの改善によって不良率が大幅に低下した場合や、市場からより高い品質要求が出てきた場合には、AQLや検査水準を定期的に見直すことが、品質とコストのバランスを常に最適に保つ上で重要です。
抜き取り検査と統計的品質管理(SQC)
抜き取り検査は、ロットの「合否判定」を行う出口管理の手法です。一方で、統計的品質管理(SQC: Statistical Quality Control)には、管理図のように製造工程そのものが安定しているかを監視する工程管理(プロセス管理)の手法もあります。
管理図によって工程が安定していることを常に監視し、その上で抜き取り検査によってロットの品質を保証する。この2つを組み合わせることで、不良品の発生を川下で防ぐだけでなく、そもそも不良を生まない安定した製造プロセスを構築・維持することが可能になります。
抜き取り検査の限界と、これからの品質保証のカタチ
抜き取り検査は非常に有用な手法ですが、万能ではありません。その限界を理解し、次世代の品質保証を見据えることも、技術者にとって重要な視点です。
抜き取り検査では原理的に防げない「不良品流出のリスク」
最大の限界は、統計的な手法である以上、不良品の流出リスクをゼロにできないことです。サンプルに含まれなかった不良品は、発見することができません。特に、安全性が最優先される製品や、極めて低い不良率が求められる製品において、このリスクは無視できない課題となります。
人による判定のばらつき(官能検査の課題)
外観検査など、人の目や感覚に頼る官能検査では、検査員の熟練度や体調、集中力によって判定基準にばらつきが生じがちです。「この傷は重欠点か、軽欠点か」といった判断が曖昧になり、品質の安定性を損なう原因となります。
画像処理・光学測定装置が実現する「検査の自動化・高速化」
人による官能検査の課題を解決するのが、画像処理や光学測定装置による検査の自動化です。 高解像度カメラとAIを用いた画像処理システムは、ミクロン単位の傷や異物を、設定された基準に基づき、24時間365日、一定の精度で検出し続けます。これにより、判定のばらつきをなくし、検査結果の信頼性を飛躍的に高めることができます。
全数検査へのシフトと、データ活用による未来の品質予知
これまでコストや時間の問題で不可能とされてきた全数検査も、高速な測定・検査装置の登場によって現実的な選択肢となりつつあります。
さらに、全数検査によって得られる膨大な品質データは、単なる合否判定に留まりません。これらのデータを解析し、製造条件のわずかな変化と不良発生の相関関係を見つけ出すことで、不良が発生する予兆を捉え、未然に防ぐ「品質予知」も視野に入ってきます。これは、事後処理であった品質管理を、未来志向のプロアクティブな活動へと進化させる大きな可能性を秘めています。
まとめ
本記事では、製造業の技術者が知るべき抜き取り検査の基準について、その重要性から国際指標であるAQL、JIS Z 9015の具体的な使い方、そして未来の品質保証のあり方までを網羅的に解説しました。
まずは、貴社の現在の抜き取り検査基準が、どのような根拠に基づいて設定されているかを見直すことから始めてみてはいかがでしょうか。そして、品質保証体制のさらなる高度化を目指す上で、検査の自動化やデータ活用という新たな選択肢をご検討いただく一助となれば幸いです。



