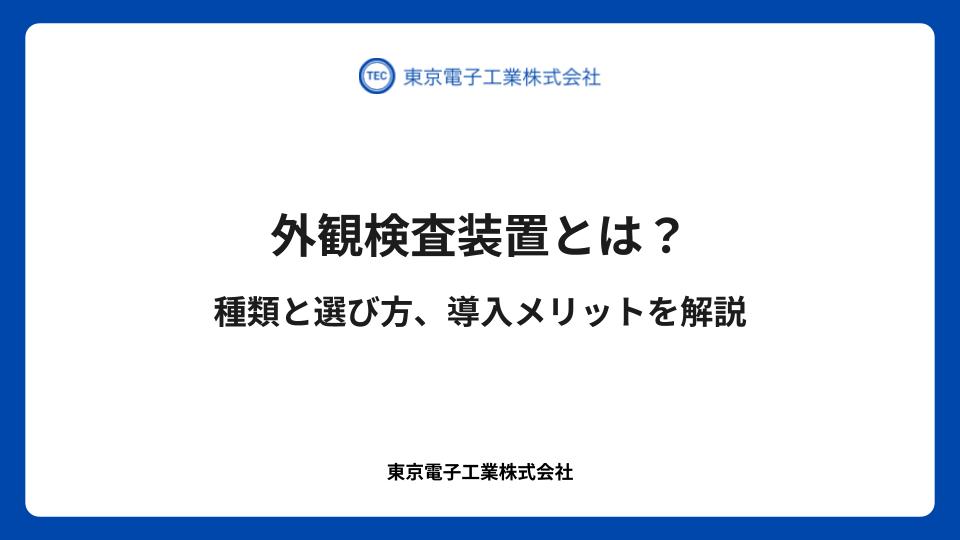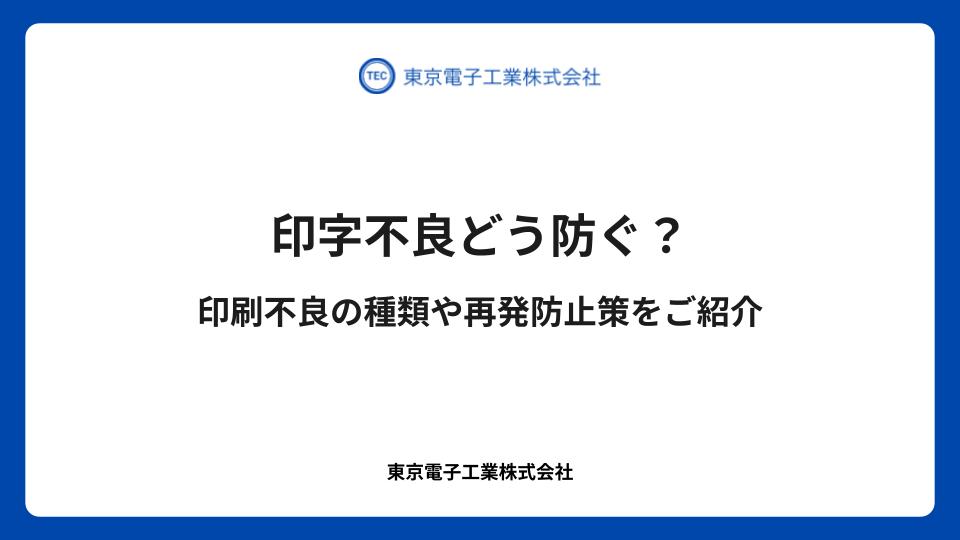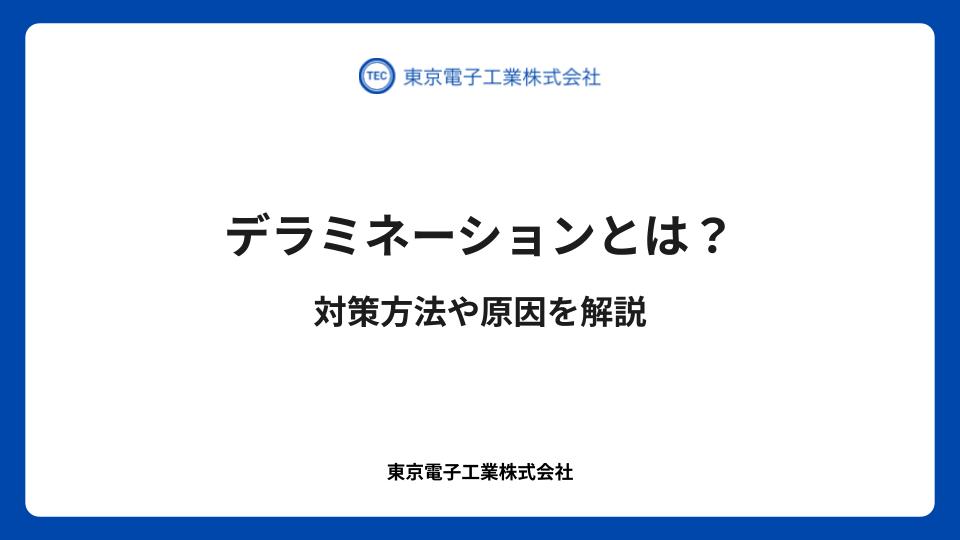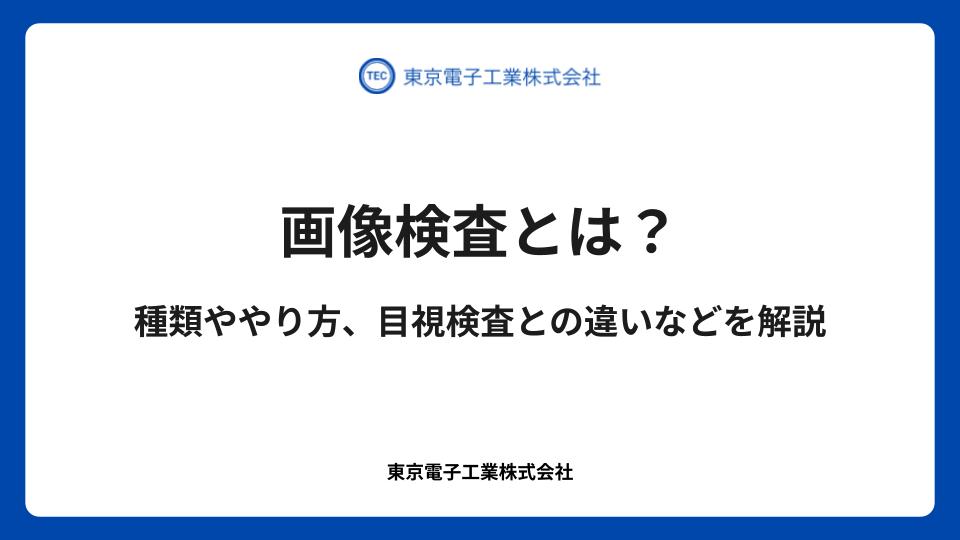
製造業において品質管理は企業の競争力を左右する重要な要素です。特に印刷物や製品の外観品質を保つために、従来の目視検査から画像検査への移行が急速に進んでいます。
本記事では、画像検査の基本概念から具体的な種類、実装方法、そして目視検査との比較までを網羅的に解説します。
画像検査とは
画像検査の基本概念
画像検査とは、カメラやセンサーを用いて対象物を撮影し、その画像データをコンピューターで解析することで、製品の品質や状態を自動的に判定する技術です。人の目視に頼ることなく、非接触かつ客観的に検査を行うことが可能であり、製造工程における不良品の検出、部品の寸法測定、文字の読み取りなど、多岐にわたる用途で活用されています。
この技術は、事前に設定された基準やアルゴリズムに基づき、画像内の欠陥(キズ、汚れ、異物など)、形状の異常、寸法の誤差、文字の誤りなどを自動で認識・判別します。これにより、検査の属人性を排除し、安定した品質管理を実現します。
画像検査が注目される背景
近年、画像検査が注目される背景には、いくつかの要因があります。まず、製造業における品質要求の高度化と、グローバル競争の激化により、より厳格で効率的な品質管理が求められています。また、少子高齢化に伴う人手不足は、製造現場での検査業務の自動化・省人化を加速させる必要性を生んでいます。
さらに、AI(人工知能)やディープラーニングといった画像処理技術の飛躍的な進化も、画像検査の性能向上に大きく貢献しています。これにより、これまで人手に頼らざるを得なかった複雑な検査や、微細な欠陥の検出も、高精度かつ高速に自動で行えるようになり、製造業のデジタルトランスフォーメーション(DX)推進の重要な要素となっています。
製造業における画像検査の重要性
製造業において画像検査は、製品の品質保証と生産性向上に不可欠な技術です。不良品の市場流出を未然に防ぎ、企業のブランドイメージと顧客からの信頼を維持する上で極めて重要な役割を果たします。また、検査工程の自動化により、人件費の削減や検査速度の向上、24時間体制での連続稼働が可能となり、生産ライン全体の効率化とコスト削減に貢献します。
加えて、画像検査で得られたデータは、品質改善のための貴重な情報源となります。不良発生の原因分析や、工程の最適化に活用することで、歩留まりの向上や製造プロセスの改善サイクルを加速させることができます。このように、画像検査は単なる不良品検出にとどまらず、製造業の競争力強化に直結する戦略的なツールとしてその重要性を増しています。
画像検査の種類
外観検査
外観検査は、製品の表面に現れる傷、汚れ、異物、欠け、変形、色ムラといった不良を検出する検査です。製造業における品質保証の根幹をなす検査であり、人の目では見落としがちな微細な欠陥や、高速生産ラインにおける全数検査を自動化することで、不良品の流出を未然に防ぎます。
電子部品の半田付け不良、自動車部品の表面キズ、食品パッケージの印字欠けなど、幅広い製品で適用され、画像処理技術を用いてこれらの欠陥を正確に識別します。
寸法検査
寸法検査は、製品の長さ、幅、高さ、直径、穴の位置、角度などの幾何学的寸法が、設計図や規格に合致しているかを確認する検査です。精密な部品製造において、寸法の狂いは製品の機能不全や組み立て不良に直結するため、非常に重要です。
画像検査では、高解像度カメラで撮影した画像から、キャリブレーションされたピクセル情報に基づいて実寸を計測します。これにより、非接触で高速かつ高精度な寸法測定が可能となり、ノギスやマイクロメーターといった手動測定器では困難な複雑な形状や微細な部品の検査も自動化できます。
文字・印字検査
文字・印字検査は、製品に印字されたロット番号、製造年月日、賞味期限、バーコード、QRコード、ロゴ、製品名などが、正しく、鮮明に、かつ指定された位置に印字されているかを検証する検査です。特に食品、医薬品、化粧品など、トレーサビリティや法令順守が厳しく求められる分野で不可欠です。
光学文字認識(OCR: Optical Character Recognition)や光学文字検証(OCV: Optical Character Verification)技術を用いて、文字の読み取り、誤字脱字、かすれ、にじみ、欠け、位置ずれなどを検出します。また、バーコードやQRコードの読み取り品質も同時に評価し、物流や情報管理の信頼性を高めます。
色彩検査
色彩検査は、製品の色が基準色と一致しているか、あるいは色ムラがないかを確認する検査です。製品の外観品質やブランドイメージに直結するだけでなく、食品の鮮度や工業製品の機能性を示す指標となる場合もあります。
画像処理システムは、RGB(赤・緑・青)やHSV(色相・彩度・明度)、Lab(L*a*b*)といった色空間のデータを用いて、検査対象の色情報を数値化し、あらかじめ設定された基準色との差を検出します。これにより、人間の目では判別しにくい微妙な色差や、生産ラインにおける色の一貫性を高精度に管理できます。
パターンマッチング検査
パターンマッチング検査は、あらかじめ登録された基準となる画像パターン(テンプレート)と、検査対象の画像とを比較し、その一致度を評価する検査です。主に部品の有無、位置ずれ、向きのずれ、種類の判別などに用いられます。
この技術は、製造ラインにおける部品の組み付け確認、電子基板上の部品実装位置の確認、欠品検出、あるいはロボットのビジョンシステムにおける対象物の認識と位置決めなど、多岐にわたる自動化工程で活用されます。高速かつ高精度なパターン認識により、生産効率と品質の向上に貢献します。
画像検査のやり方・実装方法
システム構成の基本要素
画像検査システムを導入する際には、複数の要素が連携して機能するシステムを構築する必要があります。主な構成要素としては、検査対象物を撮影する「カメラ」、光を当てる「照明」、カメラから得られた画像を処理・解析する「画像処理ユニット(PC)」、そしてそれらを制御する「画像処理ソフトウェア」が挙げられます。
これらに加え、検査対象物をカメラの視野に正確に位置させるための「搬送装置」や「ロボット」、検査結果に基づいて良品・不良品を仕分けるための「排出機構」などが組み合わされることで、自動化された画像検査システムが完成します。各要素は検査対象物や検査内容、求められる精度に応じて最適なものが選定されます。
カメラの選定
カメラは画像検査システムの「目」となる重要な要素です。検査対象物の特徴や検査内容に応じて、適切な種類のカメラを選定する必要があります。
エリアスキャンカメラ
一般的なデジタルカメラと同様に、一度に広範囲を撮影します。静止している対象物や、広範囲の欠陥を検査するのに適しています。解像度、フレームレート、センサーサイズ、カラー/モノクロなどの仕様が重要です。
ラインスキャンカメラ
細い線状の領域を連続的に撮影し、画像を繋ぎ合わせて一枚の画像を作成します。高速で移動する対象物や、ロール状の素材(フィルム、シートなど)の検査に多く用いられます。
また、インターフェース(GigE Vision, USB3 Visionなど)や、検査対象物の色や質感に応じたカラーカメラまたはモノクロカメラの選択も重要です。レンズはカメラと検査対象物の距離、視野、必要な解像度に合わせて、焦点距離やF値、歪曲収差の少ないものが選ばれます。
照明の選定
照明は検査対象物の特徴を際立たせ、安定した画像を取得するために不可欠です。照明の種類や設置方法によって、検査の成否が大きく左右されます。
リング照明
カメラの周囲から光を当てるため、均一な照明が得やすく、一般的な外観検査に適しています。
バー照明
特定の方向から光を当てることで、傷や凹凸の影を強調したり、光沢面のハレーションを抑えたりするのに有効です。
ドーム照明
半球状の内部で光を拡散させることで、光沢のある対象物や曲面を持つ対象物に対しても、影やハレーションの少ない均一な照明を実現します。
バックライト
対象物の輪郭や穴の有無、透明なものの異物検査などに用いられます。対象物の背後から光を当てることで、シルエットを鮮明に捉えます。
さらに、照明の色(白色、赤色、青色など)も、検査対象物の色や材質、検査したい特徴に応じて使い分けられます。
画像処理ソフトウェアの設定
画像処理ソフトウェアは、カメラが取得した画像を解析し、良品・不良品の判定を行うための「頭脳」です。多くのプロフェッショナルな画像処理ライブラリやパッケージ(例:Halcon、VisionProなど)が市場に流通しており、またオープンソースのライブラリ(例:OpenCV)も活用されています。
ソフトウェアでは、まずノイズ除去やコントラスト調整といった前処理を行い、その後に検査目的に応じたアルゴリズムを適用します。
例えば、エッジ検出、二値化、ブロブ解析(連結成分解析)、パターンマッチング、寸法計測、OCR(文字認識)などが基本的な処理です。近年では、AI(人工知能)やディープラーニングを活用したソフトウェアも登場し、複雑な外観検査や、人間の目では判断が難しい微細な欠陥の検出、多様な不良品の分類など、より高度な検査が可能になっています。
これらのソフトウェアは、GUI(グラフィカルユーザーインターフェース)を通じて設定を行うものや、プログラミング言語(C++, Pythonなど)を用いてカスタマイズするものがあります。検査の精度と安定性を高めるためには、適切なアルゴリズムの選択と、パラメータの綿密な調整が不可欠です。
目視検査との違い
検査精度の比較
画像検査は、カメラと画像処理技術を用いることで、人間の目では捉えにくい微細な欠陥や色のわずかな違いも客観的かつ定量的に検出できます。設定された基準に基づき一貫した検査を行うため、検査結果にばらつきが生じにくいのが特徴です。
特に、AI(人工知能)やディープラーニングを組み合わせることで、複雑な欠陥パターンも高精度に識別できるようになり、熟練者の判断を超える精度を実現するケースも増えています。
一方、目視検査は人間の感覚と判断に依存するため、検査員の熟練度、集中力、体調によって精度が大きく変動します。長時間の作業による疲労や、個人間の判断基準のばらつきは、見落としや過剰な不良判定につながるリスクがあります。微細な欠陥や高速で流れる製品の検査では、物理的に限界が生じることも少なくありません。
検査速度と効率性
画像検査システムは、高速カメラと高性能な画像処理ユニットにより、1秒間に数十個から数百個といった非常に速い速度で製品を検査できます。24時間体制での連続稼働が可能であり、大量生産ラインにおける全数検査を効率的に実現します。これにより、生産スループットを落とすことなく品質保証を行うことができ、生産性向上に大きく貢献します。
目視検査は、本質的に人間の作業速度に制約されます。検査対象の複雑さや数によっては、検査に要する時間が長くなり、生産ラインのボトルネックとなる可能性があります。また、検査員には定期的な休憩が必要であり、24時間稼働には多くの人員配置が求められるため、効率性には限界があります。
コスト面での比較
画像検査の導入には、カメラ、照明、画像処理ソフトウェア、PC、ロボットなどの初期設備投資が必要です。また、システムの構築や調整、保守にも費用がかかります。しかし、長期的には人件費の削減、不良品流出によるクレームやリコール費用の抑制、生産性向上による利益増加など、多くのコストメリットが期待できます。特に、人手不足が深刻化する中で、自動化による人件費抑制効果は無視できません。
目視検査は、初期投資は少ないものの、継続的な人件費が発生します。検査員の採用、教育、福利厚生などにかかる費用は、長期的に見ると高額になる場合があります。また、ヒューマンエラーによる不良品流出が発生した場合、その損害賠償やブランドイメージ低下による機会損失は、計り知れないコストとなる可能性があります。
人的要因の影響
画像検査は、設定されたアルゴリズムとパラメータに基づいて客観的に検査を行うため、検査結果に人的要因が影響することはありません。これにより、常に安定した品質基準を保つことができ、検査員の熟練度や体調に左右されることなく、一貫した品質管理が可能です。
目視検査は、検査員の集中力、疲労度、経験、さらには個人的な感情や主観といった人的要因に大きく左右されます。長時間の単調な作業は集中力低下を招き、見落としや誤判定のリスクを高めます。また、熟練者と新任者では検査能力に差が生じやすく、品質の均一性を保つことが困難になることがあります。
データ蓄積・分析機能
画像検査システムは、検査結果をデジタルデータとして自動的に記録・蓄積します。これにより、いつ、どの製品の、どのような不良が検出されたかといったトレーサビリティが確保されます。蓄積されたデータは、不良発生の傾向分析、工程改善、品質向上へのフィードバック、さらには予防保全や予知保全といった高度な品質管理に活用できます。
目視検査の場合、検査結果の記録は手作業で行われることが多く、データの蓄積や分析が困難です。記録が不完全であったり、デジタル化されていなかったりすると、品質改善のための具体的な根拠を見つけ出すのが難しくなります。結果として、不良発生の原因究明や再発防止策の立案が遅れる可能性があります。
まとめ:画像検査装置を活用しよう
本記事では、画像検査の基本概念から種類、実装方法、そして目視検査との具体的な違いまでを解説しました。画像検査は、製造業における品質管理に不可欠な技術であり、外観、寸法、文字など多様な検査を高い精度と安定性で自動化します。目視検査と比較し、人的ミスを排除し、検査速度と効率性を飛躍的に向上させることで、製品品質の安定化、生産性の改善、コスト削減に大きく貢献します。
東京電子工業では、お客様の生産ラインに合わせた最適な画像検査システムを柔軟に設計・提供しています。一般的な外観検査はもちろん、特に、紙媒体の検査に強みを持っており、混入検査、糊検査、2枚検査といった独自のソリューションをご用意しています。
長年の開発で培ったノウハウと柔軟な対応力で、お客様の多様なニーズに応える「オーダーメイド」の画像検査機をご提供します。品質管理の課題解決に向けて、ぜひ東京電子工業にご相談ください。
東京電子工業の製品紹介はこちら
https://www.t-denshi-k.co.jp/products.html
発注から納品までの流れはこちら
https://www.t-denshi-k.co.jp/flow.html