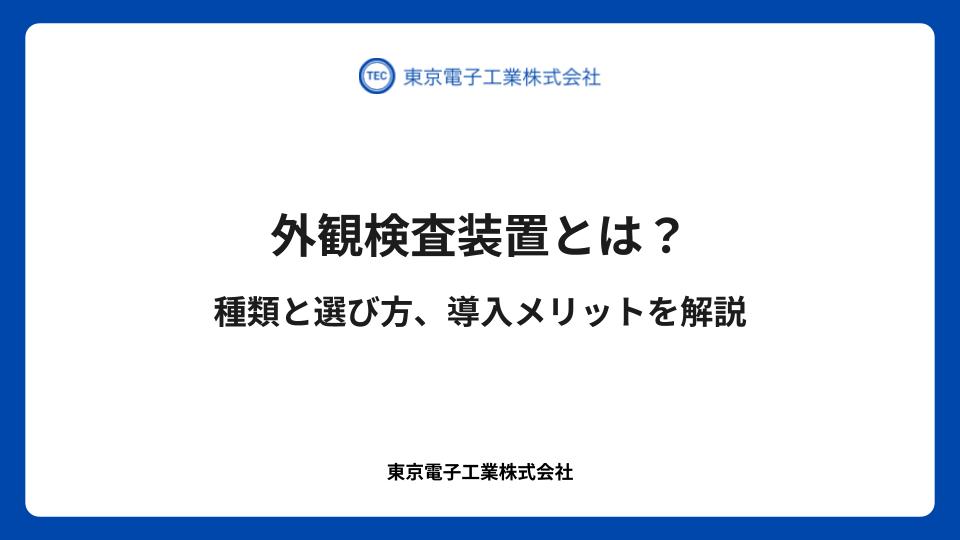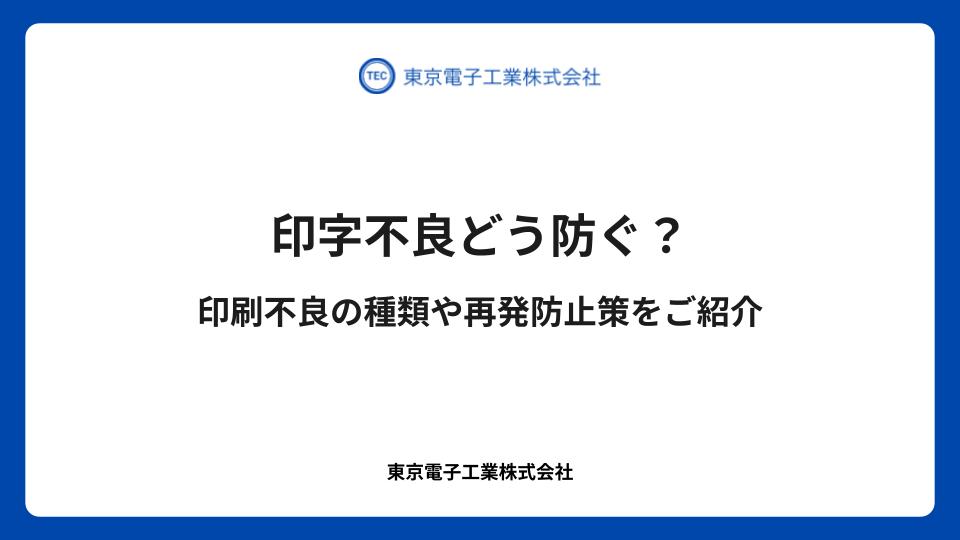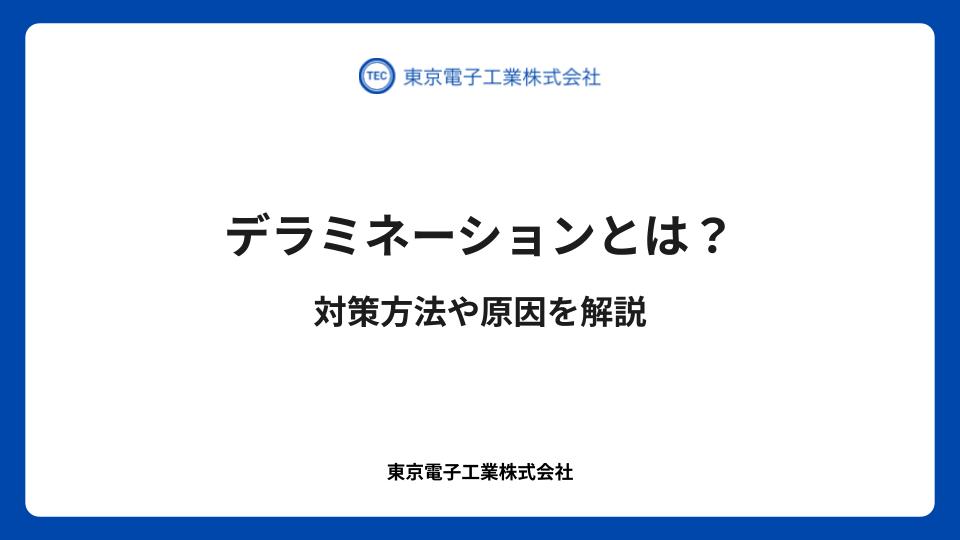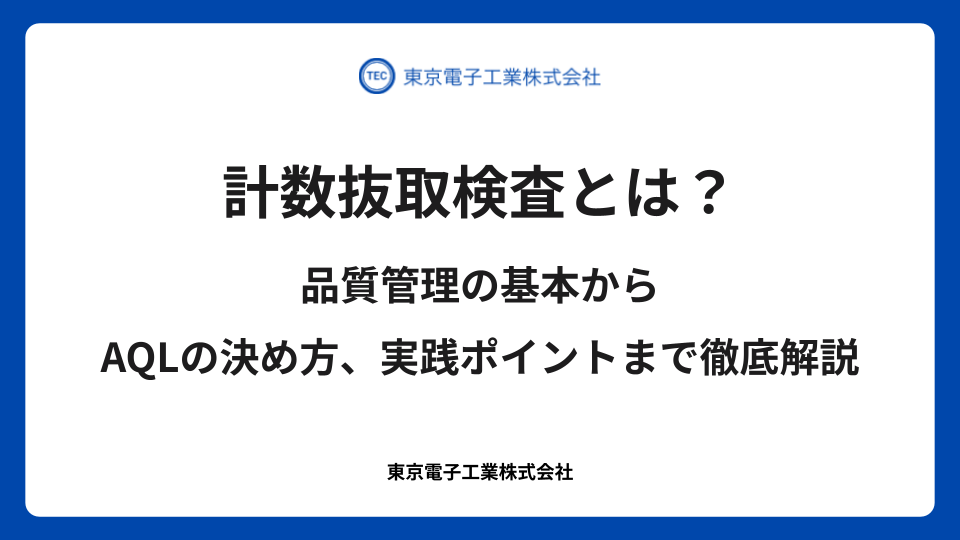
製造業の品質管理において、「全数検査」によるコスト増や工数の肥大化に課題を感じていませんか?あるいは、「抜取検査」を導入しているものの、その基準や手法が属人化し、客観的な品質保証ができているか不安に思うことはないでしょうか。
計数抜取検査(けいすうぬきとりけんさ)は、国際規格(ISO)やJIS規格にも定められた統計学的な品質管理手法であり、コストと品質の最適なバランスを実現するための強力なツールです。
この記事では、大手製造業の技術部門で品質管理に携わる方に向けて、計数抜取検査の基本的な概念から、検査レベルやAQL(合格品質水準)といった具体的な基準の決め方、そして現場で成果を出すための実践的なポイントまでを、図解を交えながら体系的に解説します。
本記事を読めば、貴社の製品品質と生産性をさらに一段高いレベルへ引き上げるための、確かな知識と具体的なアクションプランが手に入ります。
関連記事:抜き取り検査とは?目的、種類、全数検査との違いを徹底解説
計数抜取検査とは?~なぜ今、改めて注目されるのか~
まず、計数抜取検査がどのようなもので、なぜ多くの製造現場で採用されているのか、その基本的な概念から確認していきましょう。
計数抜取検査の基本的な定義
計数抜取検査とは、生産された製品のロット(集合)から、あらかじめ定められた数のサンプルをランダムに抜き取り、その中に含まれる不良品の個数を数えて、ロット全体の合否を判定する検査方法です。
JIS Z 8101-2(統計用語−第2部:統計的品質管理)では、「抜取検査において,アイテムを良品又は不良品に分類し,サンプル中の不良品の個数(又は,100アイテム当たりの不適合の個数)をロットの合否判定基準と比較してロットの合否を判定する方法」と定義されています。
簡単に言えば、「いくつかのサンプルを調べて、不良品の数が基準より少なければ、そのロットは丸ごと合格とみなす」という、統計学に基づいた合理的な品質管理手法です。
なぜ抜取検査が必要なのか?全数検査との比較
品質を保証するなら、すべての製品を検査する「全数検査」が最も確実だと考えがちです。しかし、全数検査には多くの課題が伴います。計数抜取検査がなぜ必要なのか、全数検査と比較してみましょう。
| 比較項目 | 計数抜取検査 | 全数検査 |
|---|---|---|
| 検査コスト | ◎ 低い(一部のサンプルのみ) | × 高い(全製品が対象) |
| 検査時間 | ◎ 短い | × 長い |
| 人的ミス | ○ 少ない(検査数が少ないため) | △ 多い(長時間の単純作業で発生) |
| 破壊検査 | ◎ 可能 | × 不可能(全製品が破壊される) |
| 品質保証 | ○ 統計的に保証(100%ではない) | ◎ 原則100%保証(見逃しリスクあり) |
ご覧の通り、計数抜取検査はコストと時間の面で圧倒的に有利です。また、製品を破壊しなければ性能がわからない場合(例:食品の味、電子部品の寿命、ネジの強度など)では、抜取検査でなければ製品として出荷すること自体ができません。
計量抜取検査との違いとは?
抜取検査には「計数抜取検査」と「計量抜取検査」の2種類があります。この違いを理解することは、適切な検査方法を選ぶ上で非常に重要です。
- 計数抜取検査: 不良品の個数を数える検査(例:傷の有無、ネジの欠品、印刷のかすれ)。判定基準が「OK/NG」で明確なため、検査が比較的容易です。
- 計量抜取検査: 製品の特性値(長さ、重さ、硬度など)を測定し、その測定値が規格を満たしているかで判断する検査。より少ないサンプル数で高い精度の保証が可能ですが、測定に手間がかかる場合があります。
| 検査方法 | 判定基準 | 特徴 |
|---|---|---|
| 計数抜取検査 | 個数(OK/NG、良品/不良品) | 判定が容易、多くのサンプルが必要 |
| 計量抜取検査 | 測定値(長さ、重さ、電圧など) | 少ないサンプルで高精度、測定に手間 |
本記事では、より多くの現場で汎用的に用いられている計数抜取検査を中心に解説を進めます。
国際規格ISOやJIS規格における位置づけ
計数抜取検査は、個々の企業の独自ルールではなく、世界的に標準化された手法です。
- ISO 2859シリーズ: 計数抜取検査の手順について規定した国際規格。
- JIS Z 9015シリーズ: 上記ISOに準拠して作成された日本産業規格(JIS)。
これらの規格に則って検査を行うことで、客観的で信頼性の高い品質保証が可能となり、サプライヤーと顧客間の取引もスムーズになります。
計数抜取検査のメリット・デメリット
計数抜取検査は万能ではありません。そのメリットとデメリットを正しく理解し、特性を活かすことが重要です。
【メリット】コスト削減と検査時間短縮
最大のメリットは、前述の通り、検査対象がロットの一部であるため、検査にかかるコスト(人件費、設備費)と時間を大幅に削減できる点です。これにより、生産性の向上に直接的に貢献します。
【メリット】破壊検査にも適用可能
製品の強度、寿命、成分などを調べる「破壊検査」において、全数検査は不可能です。抜取検査であれば、一部のサンプルを犠牲にするだけでロット全体の品質を推定できるため、破壊検査が必須の製品でも品質保証が可能になります。
【デメリット】ロットの品質を100%は保証しない
これは最も注意すべき点です。抜取検査はあくまで統計的な推定であるため、合格したロットの中に、ある程度の不良品が含まれる可能性(リスク)を許容することが前提となります。このリスクを「買い手危険(Consumer's Risk)」と呼びます。
【デメリット】ロットの品質が悪いと見逃しのリスクも
ロット全体の不良率が極端に高い場合、偶然抜き取ったサンプルに不良品が含まれず、本来不合格とすべきロットを合格としてしまうリスク(売り手危険/Producer's Risk の逆)もゼロではありません。そのため、安定した製造工程を維持することが大前提となります。
【実践編】計数抜取検査の進め方と基準の決め方
ここからは、実際に計数抜取検査をどのように進めていくのか、具体的な手順と基準の決め方を解説します。
検査の全体フロー(5ステップで解説)
計数抜取検査は、基本的に以下の5つのステップで進められます。
- ロットの形成: 生産条件(機械、原料、日時など)が同じ製品群を一つの「ロット」としてまとめる。
- 抜取方式の決定: AQLや検査レベルなど、検査の厳しさを決定する。
- サンプルの抜取: 決定した方式に基づき、ロットから規定数のサンプルをランダムに抜き取る。
- 検査と不良品数のカウント: 抜き取ったサンプルを検査し、不良品の個数を数える。
- ロットの合否判定: 不良品の数が合格判定個数以下であればロットを「合格」、不合格判定個数以上であれば「不合格」とする。
最も重要な指標「AQL(合格品質水準)」とは?
AQL(Acceptable Quality Level)は「合格品質水準」と訳され、計数抜取検査において最も重要な指標です。これは、「このくらいの不良率までなら、そのロットを合格とみなしても良い」と、生産者と顧客(買い手)の間で合意する品質レベルの上限値を指します。
AQLは「このロットの品質はAQL%である」という保証ではなく、「AQL%の不良率であるロットが検査に合格する確率が非常に高くなるように設計された検査方式」と理解することが重要です。
AQLの具体的な決め方と業界別の目安
AQLは、製品の重要度、安全性、コストなどを考慮して決定されます。
- 重要保安部品(自動車のブレーキなど): 非常に厳しいAQL(例:0.01%~0.4%)が設定される。
- 機能部品(一般的な機械部品など): 標準的なAQL(例:0.65%~1.5%)が設定される。
- 外観部品(軽微な傷や汚れなど): 比較的緩やかなAQL(例:2.5%~4.0%)が設定される。
最終的には、取引先との契約や、社内の品質基準に基づいて決定します。
検査レベル(通常検査・きつい検査・ゆるい検査)の選び方
JIS Z 9015では、ロットの品質履歴に応じて検査の厳しさを変える「検査レベル」が定められています。
- 通常検査: 基本となる検査レベル。
- きつい検査: 品質が悪いロットが続いた場合に適用。通常検査より厳しい基準(少ない不良品数で不合格)になる。
- ゆるい検査: 品質の良いロットが続いた場合に適用。通常検査より少ないサンプル数で検査が可能。
この他に、検査コストを低く抑えたい場合に用いる「特別検査レベル(S-1~S-4)」もあります。
計数抜取検査の精度と効率を高める3つのポイント
理論通りに運用しても、現場での実践方法が正しくなければ計数抜取検査は機能しません。精度と信頼性を高めるための重要な3つのポイントを紹介します。
ポイント①:ロット形成のルールを明確にする
抜取検査の精度は、ロット内の品質が均一であることが大前提です。異なる生産ラインや異なる時間帯に作られた製品を一つのロットに混ぜてしまうと、統計的な妥当性が失われます。 「同じ原料、同じ機械、同じ作業者、連続した時間帯」など、品質が均質とみなせる単位でロットを形成するルールを明確に定め、遵守することが不可欠です。
ポイント②:ランダムサンプリングを徹底する
サンプルを抜き取る際に、意図が入ってはいけません。「箱の上の方だけ」「取りやすい場所から」といった抜き取り方では、ロット全体を代表するサンプルとは言えません。 乱数表を用いたり、ロット全体に番号を振ってランダムに指定したりするなど、すべての製品が等しい確率で選ばれる「ランダムサンプリング」を徹底してください。
ポイント③:検査員のスキルや判断基準のバラつきをなくす
特に目視による外観検査では、「この程度の傷は許容範囲か?」といった検査員の主観による判断のバラつきが、品質保証における最大のリスクとなり得ます。 熟練者と新人で見解が分かれては、計数抜取検査の信頼性は揺らぎます。限度見本の整備、判断基準を明記した作業標準書の作成、定期的な研修などを通じて、誰が検査しても同じ結果になる体制を構築することが重要です。
品質管理の未来:画像処理による計数抜取検査の自動化
前章で述べたような「人的な課題」は、多くの製造現場が抱える共通の悩みです。その根本的な解決策として、今、画像処理技術を用いた検査の自動化が急速に普及しています。
人の手による抜取検査の限界とは?
人による検査には、どうしても避けられない限界があります。
- ヒューマンエラー: 熟練者であっても、疲労や集中力の低下による見逃しは発生します。
- 判定基準のブレ: 「ポイント③」で述べた通り、官能検査における判断の個人差は避けられません。
- 記録の手間とミス: 検査結果を手作業で記録・転記する際に、ミスや漏れが発生する可能性があります。
これらの課題は、品質の安定性を損なうだけでなく、トレーサビリティを確保する上での大きな障壁となります。
画像処理・光学測定装置がもたらすメリット
こうした人の手による検査の限界は、当社の画像処理装置や光学測定装置によって解決できます。
高速かつ高精度な判定で、検査レベルを向上
人の目では捉えきれない微細な欠陥も、高解像度カメラとAIが瞬時に検出。検査精度が飛躍的に向上し、より厳しいAQLや検査レベルの適用が可能になります。
判定基準の均一化と検査データの自動記録
あらかじめ設定した基準に基づき、AIが常に一定の基準で合否を判定。判断のブレは一切ありません。さらに、検査結果(OK/NG、不良内容、日時など)はすべて自動でデータとして記録・蓄積されます。
トレーサビリティの確保と品質改善へのデータ活用
蓄積された検査データは、不良発生時の原因究明(トレーサビリティ)を容易にします。さらに、データを分析することで、特定の工程や条件で不良が多発する傾向を掴み、製造プロセスそのものを改善する貴重な情報資産となります。
貴社の品質管理を次のステージへ
計数抜取検査の課題を解決し、品質と生産性を飛躍的に向上させる「検査の自動化」。 貴社の製品や検査工程に合わせた最適なソリューションをご提案します。ぜひ、お気軽にご相談ください。
当社の画像処理・光学測定装置ラインナップを見る
https://www.t-denshi-k.co.jp/products.html
品質管理の自動化に関するご相談はこちら
https://www.t-denshi-k.co.jp/contact.html
まとめ
本記事では、計数抜取検査の基本的な考え方から、JIS規格に基づいた実践的な進め方、そして精度を高めるためのポイントまでを網羅的に解説しました。
- 計数抜取検査は、コストと品質のバランスを取るための合理的な手法である。
- AQLや検査レベルを正しく設定し、JIS Z 9015の抜取表に沿って運用することが基本となる。
- ロット形成とランダムサンプリング、判定基準の統一が、検査の信頼性を担保する上で極めて重要である。
- 人の手による検査の限界(ヒューマンエラー、基準のブレ)は、画像処理技術による自動化で解決できる。
計数抜取検査を正しく理解し、さらにテクノロジーの力でその精度と効率を高めることが、これからの製造業における競争力の源泉となります。この記事が、貴社の品質管理体制を見直し、改善していくための一助となれば幸いです。